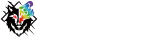Interview
中島清吉商店
「統一された40枚の駒」木地師の力
中島清吉商店のはじまり
中島清吉商店の創業は、幕末生まれの曾祖父、為三郎にさかのぼります。為三郎は武家の三男であり、明治維新により職を失いました。その後、天童織田藩の武士たちが内職として行っていた将棋駒作りに着目し、1880年にその事業を始めたことが、中島清吉商店の創業のきっかけとなりました。
武士たちの内職

さくらんぼや温泉、そして将棋の街として知られる山形市の北に位置する天童市。
江戸時代、武士たちの内職として将棋駒の製作が奨励されたことがきっかけとなり、今では全国の将棋駒生産の9割以上を誇ります。町の至るところに「将棋」の文字や将棋駒を模したオブジェが点在し、国に指定された伝統的工芸品が生み出されています。そんな天童市に、暖簾を掲げるのが、「中島清吉商店」です。
一駒・約3㎝に込めるこだわり
中島清吉商店の将棋駒は、3つの基本軸に基づいて製造されています。
①国産材の使用
②一貫した製造工程
③伝統技術の継承
これら3つを大切にし、140年にわたる歴史を繋いできました。最高品質を維持しつつ、時代ごとの新しい提案を行い、腕の良い彫り師たちと共に「天童将棋駒」の技術を継承しています。 彫りや漆入れといった伝統技法を駆使し、職人たちが一駒一駒を心を込めて作り上げています。
彼らの技術と情熱が、今日の「中島清吉商店」を支えています。
中島清吉商店の誇り
明治末期から機械化を進め、昭和初期には量産体制を確立し、東京や大阪の問屋へ出荷していました。しかし、平成の半ば頃に将来を見据え、品質重視の少量生産体制に移行しました。現在では、プロの対局で使用される盛り上げ駒なども製造しています。このように時代の変化に合わせて業態を進化させ、長い歴史を紡いできたことに、深い誇りを持っています。
中島清吉商店のこだわり

・月日をかけて生み出す国産の木地
将棋の駒の原料には、イタヤ、斧折、御蔵島黄楊、槐など、希少な国産の木材を使用しています。これらの木材は仕入れた後、まずは3年ほどかけて水分を完全に取り除きます。この長期間にわたる乾燥作業は、時間が経ってもシミが入ったり割れたりするのを防ぐため、駒作りにおいて最も重要な工程です。お客様の手元に届いた後、駒が変形することがないよう、しっかりと木地を乾燥させてから製品として仕上げていきます。
・木地師(きじし)の力
将棋駒の良し悪しを決める基準はさまざまですが、最も重要なのは、40枚の駒が揃った時に木目がどれだけ統一されているかという点です。特に美しいとされるのが、本ツゲ材の「虎斑」という木目模様ですが、ツゲ材には個体差があり、必ずしもすべての木材に美しい虎斑が現れるわけではありません。この木目を40枚のセットで美しく見せるために、非常に高い技術が求められます。私たち木地師は、最高の品をお客様にお届けするため、常に木地に向き合い、駒を丁寧に切り出し続けています。
・職人の「彫り」と「書き」
将棋駒は「ふ」から「王」までサイズが異なり、専用の楔で調整して固定し、左手で持ち方を変えつつ、右手で彫り進めます。字の太さに合わせて刀の深さを調整し、太い部分は深く、細い部分は薄く彫ります。何度刃を入れても、一筆で書いたような美しさに仕上げることが求められます。この技術には基本を学び、さらに10年の経験が必要ですが、それでも一流には近づけません。私たちは「常に完璧に仕上げる」という情熱を持って、日々最高の仕上がりをイメージしながら取り組んでいます。
最も大変なこと
木地を1セット同じような色木目で揃えることが、最も大変な作業です。将棋駒は、木目や色合いが揃っていることでより美しさが際立ちます。
困りごと
現在、作り手の不足が大きな課題となっています。
高い技術を持った職人の育成や確保が難しく、今後の技術継承が心配されます。
将棋の使い方

将棋のルールがわからなくても大丈夫です。ハサミ将棋、回り将棋、山崩しなど、簡単なゲームがいくつもあり、初心者でも楽しめる方法で将棋の魅力を感じることができます。
これからどんな狼煙をあげていきますか?
現在は将棋ブームの真っ只中で、私たちが作ったものが売れる時代です。
いずれはそのブームも落ち着くと思っているので、今後は世界中に将棋ブームを起こし、将棋の魅力を広げていくことが目標です。
記事協力企業
本記事は、【中島清吉商店】のご協力のもと作成いたしました。
▼中島清吉商店公式HPはこちら
日本文化継承プロジェクト狼煙 -NOROSHI-

狼煙 -NOROSHI- は、日本文化の魅力を発信し、次世代へと継承していく取り組みを続けています。
また、日本の伝統工芸品の魅力を伝えるため、無料で記事作成を行っています。
「もっと多くの人に伝えたいことがある」
「日本文化を広める手伝いをしてほしい」
そんな想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
📩 お問い合わせはこちら