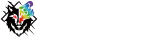Interview
副島硝子工業株式会社
「肥前びーどろ」世界で唯一の工房
肥前びーどろのはじまり
佐賀(鍋島)藩10代藩主鍋島直正公が、嘉永五年(1852)多布施川のほとりに精煉方(現理化学研究所)を設置したことが始まりと言われています。精煉方は、生活必需品(金魚鉢・薬瓶・銘酒瓶など)や、学術研究所のために必要な道具を作った場所で、実験の為のビーカーやフラスコを作るため当時では珍しいガラス窯が築かれました。
その後、開国・明治維新に入り精煉方は、民間会社(精煉所)となり、明治36年に副島源一郎が独立し「副島硝子工業」を創業しました。現在では肥前びーどろを製造する唯一の工房です。
副島硝子工業で製造するガラス製品
種類
・肥前びーどろ(タンブラー)
・鉢
・皿などの器
特徴
宙吹き:型を用いずに僅かな道具を使い、職人の技術のみで成形していく技法です。
宙空で成形する為、その形一つ一つに違いが生まれます。その形はどこか自然で優しい風合いをおび、表面は滑らかで艶のあるものとなります。
魅力
職人の高い技術が要求されるため、1個として同じものは仕上がりません。
オートメーションでは出来ないような、色・形など職人の個性が出るよう差別化を図っています。
人気のあるガラス製品
虹色シリーズのタンブラー類がよく売れています。
独自の製造方法
・技術
江戸時代に始まったと言われる、ガラス製の吹き竿を使用する「ジャッパン吹き」は、風鈴を除けば世界で「副島硝子工業」のみで製造されています。その中でも一人で竿を2本持って作る「二刀流」は、特に難易度が高く習得の難しい技法です。これは胴体作成後、もう一本のガラス竿にガラスを付けて胴体に接着し注ぎ口を作っていくためです。
・こだわり
ガラスの表面をわざと凹凸や泡を入れたり、
色の変化を際立たせるよう工夫しています。
・最も重要な工程
宙吹きでは、仕上げ加工が最も難しい工程であり、ポイントになります。
一番の思い出
職人の高い技術が要求される製造方法であるため、
最初の頃はガラス作りの難しさを痛い程感じたこと。
おすすめの商品
・アクセサリー「テラス」
昨年、佐賀国スポで「肥前びーどろ」の特殊な色を使ったガラスを埋め込んだメダルが採用されました。
そのアクセサリー「テラス」などが、評判で良く売れております。
これから先、あなたはどんな狼煙を上げたいですか?
「テラス」の新商品開発を目指し、宝石箱等を作って狼煙を上げたい想いです。
世界唯一の肥前びーどろ製造を行う「副島硝子工業株式会社」は、進化の歩みを止めることなく邁進しています。
私たち「狼煙 -NOROSHI-」は、副島硝子工業株式会社の発展を心から応援しています。また日本文化の魅力を多くの人々に広め、さらに素晴らしい挑戦を続けていくことを期待しています!
記事協力企業
本記事は、【副島硝子工業株式会社】のご協力のもと作成いたしました。
▼副島硝子工業株式会社公式HPはこちら
日本文化継承プロジェクト狼煙 -NOROSHI-

狼煙 -NOROSHI- は、日本文化の魅力を発信し、次世代へと継承していく取り組みを続けています。
また、日本の伝統工芸品の魅力を伝えるため、無料で記事作成を行っています。
「もっと多くの人に伝えたいことがある」
「日本文化を広める手伝いをしてほしい」
そんな想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
📩 お問い合わせはこちら