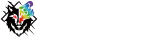Interview
阿島傘 一凛
「傘の村 一凛の軌跡」
一凛の始まり

明治40年頃、100軒以上と栄えた傘製造場。
洋傘の普及により衰退し、昭和末期には1軒だけとなりました。
その1軒残った「菅沼商店」に師事し、
傘作りを学んだ職人により「阿島傘 一凛」がはじまりました。
『阿島傘 一凛』
・特徴
阿島傘は江戸時代から喬木村に伝わる和傘で、
普段使いのシンプルな番傘が主流です。
その中でも阿島傘一凛の番傘は、飾りとしても映える色鮮やかな傘で、
セミオーダーでも注文することができます。
・こだわり
伝統的な傘の図案や日本古来の文様を活かすようにしています。
また自分だけの傘を作れるよう、
デザインシミュレーションもWEB上で提供しています。
・素材
メインで使用する和紙は長野県産の手漉き和紙で、
内山和紙と久堅和紙を使用しています。
内山和紙は長野県の伝統的工芸品にも認定されており、
久堅和紙は、古くから阿島傘に使用されてきた、
隣接する飯田市下久堅で作られる和紙になります。
・耐久性
もともと和傘は実用品ですので、使用に耐えうる耐久性を持っています。
その上で丈夫な手漉き和紙を使うことで年単位で使える番傘になっています。
・工程
材料となる骨や柄は専門の職人から購入。
それらを針と糸で組み立てるところ(骨つなぎ)から作業を行っています。
骨を均等に広げ(間割)、傘の円周と中ほどに補強の細い和紙を張り、
メインの被膜となる紙を張ります(大張)。
その後、傘の最上部の天井張り。
さらに畳んで輪で締めて形を整えた後、
油を引いて天日で干し防水性を付けます。
最後に傘の頭を紙で包んだら完成です。
制作時間
「骨の数ほど技がある」と言われるほど和傘づくりは工程が多く、
1本が完成するまでには2か月近く掛かります。
また阿島傘一凛の場合は県内産の手漉き和紙を自分で染色しているので、
そういった準備段階にも手間がかかります。
一番のこだわり
どの工程も手を抜くと次の工程に響くので、
常に次の工程を意識して製作しています。
特に「天井張り」には注意が必要です。
これが最も難しいと言われており、
直線の紙を丸く張れるように骨間に紙を押し込むようにして張ります。
・天井張りとは
傘の最上部、開閉時に可動する部分に何重にも紙を張る「天井張り」の工程です。
伝統的な技法と技術
和傘に図案を描こうとした場合、直接絵筆で絵や模様を描くこともありますが、
色の違う紙を切り絵のようにして貼り合わせることで、
図案を表現する「切り継ぎ」という技法があります。
絵筆で描くのとはまた違った「キリッ」とした雰囲気になります。
ゼロからはじめた
阿島傘作り

縁もゆかりも無い喬木村に一人で移住してゼロからのスタートで始めた阿島傘。
最初は人間関係の構築や異なる環境での生活、
慣れない傘作りの作業に戸惑うことばかりでした。
めげずに根気強く真面目に向き合って少しでも着実に一つずつ進めることで、
多くの方に受け入れて頂き、傘の技術を磨きました。
・偶然出会った協力隊
もともと東京で10年SEとして働いていましたが、
一生続けたい仕事では無いと思い退職しました。何がしたいか考えたとき、
「地方移住」と「伝統工芸品に関わる仕事」という2点を叶えたいと思いました。
偶然ネットで「喬木村で地域おこし協力隊として阿島傘」という募集を見つけて応募しました。
日本の伝統工芸品は素晴らしいものがたくさんありますが、
なかなか現代の人に魅力が伝わっていないように思います。
もちろん海外にも優れたものは多くありますが、
まず自国の魅力を知って誇りに思ってほしい。
そのために職人が一人だけになっていた阿島傘の後継者として修行・起業しました。
この先も阿島傘が途絶えないよう次の世代に残していきたいと思います。
・たくさんの支え
関東から移住して5年間地域おこし協力隊として阿島傘に関する活動や修行をしました。
その協力隊時代にお世話になった方や展示を見て下さった方から、
起業後すぐに注文をいただくことができました。
そんなたくさんの応援の力を感じて、ほんとうに有難く思いました。
長野県知事指定
伝統的工芸品認定
2024年に「阿島傘」が長野県知事指定伝統的工芸品認定を受けました。
長野県の阿部知事とお話をする機会も頂き、
東京で開催された外交官向けのレセプションパーティーのロビーにて
阿島傘を展示することができました。
多くの外国の方にも阿島傘を手に取り撮影していただき、非常に嬉しく思いました。
おすすめの利用方法
傘の販売だけでなくレンタルやイベント展示なども行っております。
結婚式の前撮りや成人式などにお使い頂くと華やかで特別な演出になります。
さいごに
これからどんな狼煙を
あげたいですか?

日本の伝統の良さを日本の人、そして海外の人に知ってほしい。
多くの伝統(祭り、芸能、工芸など)は後継者不足で次々と途絶えていっています。
途絶えてしまったものを復活することは非常に困難です。
グローバル化する世界で生き抜くためにも
「日本の文化」を誇りに思ってもらいたい。
それらの伝統には古来からの人々の考え、生き方、生活そのものが詰まっています。
職人になりたいと思ったら目指してください、いいなと思ったら発信してください、
欲しいと思ったら買ってください、面白そうと思ったら見に行ってください。
日本には価値あるものがたくさんあります。
日本に生まれて良かった、と思えるような「宝物」をぜひ見つけてください。
記事協力企業
本記事は、【阿島傘 一凛】のご協力のもと作成いたしました。
▼新日本製陶株式会社HPはこちら
日本文化継承プロジェクト狼煙 -NOROSHI-

狼煙 -NOROSHI- は、日本文化の魅力を発信し、次世代へと継承していく取り組みを続けています。
また、日本の伝統工芸品の魅力を伝えるため、無料で記事作成を行っています。
「もっと多くの人に伝えたいことがある」
「日本文化を広める手伝いをしてほしい」
そんな想いをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
📩 お問い合わせはこちら